
(一般社団法人 日本襖振興会 ホームページ動画より)

“和紙”と一言で言っても、それを定義するのは少々難しいと言わざるを得ません。一般的にはヨーロッパなどから伝わった洋紙(西洋紙)に対して日本製の紙(日本紙)のことを指す場合もありますし、和紙=日本古来の伝統的製法で作られたもの(手漉き紙など)と捉えている人もいるでしょう。和紙と称されている紙の中には、原料の種類から仕上がりの質感、見た目、用途、製法など多種多様な紙が存在します。また、生産地域によっても様々な特性があります。
そもそも“和紙”という言葉はいつから使われているのでしょう。全国手すき和紙連合会が発行する『和紙の手帖Ⅱ』によると、総称としての“和紙”は、江戸時代までの文献では見られないそうです。意外に思われますが、“西洋紙”の方が言葉としては先に使われ始めているとのこと。つまりは歴史的に見ると比較的新しい言葉だと言えます。前述の『和紙の手帖Ⅱ』によれば、<「和紙」は、日本の手漉き紙を意識した機械すきの紙を示す言葉として出発し、やがて本当の手漉き紙も含めて示すようになったようです。ですから、手漉き和紙と言って、伝統的な材料と手段でつくられた紙を示し、機械すき和紙と言って、明治以降導入された工業紙の材料と手段を利用してつくった紙を示している現在の状況は、至極自然なのかもしれません。>と述べられています。
そこで、このサイトでは日本の内装材料でもよく使用される、いわゆる“和紙”について、整理し、その特徴についてご紹介します。
現在、「明治時代に欧米から入ってきた機械抄き紙を“洋紙”と呼び、これに対し、日本で製造されていた手漉き紙を洋紙と区別するために“和紙”と呼ぶようになった」と、理解している人も多いと思います。しかし、『和紙の手帖Ⅱ』(全国手すき和紙連合会)によれば、“和紙”という言葉が登場した明治初期はこれとは少し違ったようです。以下一部引用します。
<では、洋紙についてはどうでしょうか。「和紙」と「洋紙」は、対比して使われる言葉ですが、同時期に現われた言葉はないようすです。洋紙あるいは西洋紙の言葉は、和紙よりはるかに早く見ることができます。文化二年(1805)に刊行された谷川清著の『和訓栞』に初めて西洋紙の呼称が見えますが、同じ文章の中で、和紙とは言わずに日本国の紙という使い方をしています。また、この場合の西洋紙は、手漉きの用紙を意味しています。
製紙機械を導入した当初は、手漉き和紙に似た洋紙をつくって、従来の手漉き紙の用途向けに売り込もうとしたふしがあります。和紙という言葉は、初めから機械すきの紙を対象に想定してつくられたようなのです。どうも、手漉き紙を和紙という言葉に含めて用いるようになったのは、かなり後になってからのようです。
明治四年(1872)、百武安兵衛は、前年のアメリカ視察の後、直ちに製紙会社設立と機械購入の準備に取りかかりますが、その中で彼が書いた『楮紙製造結社之義口上覚』によれば、「……漉立候西洋紙は外国人へ売渡候積り、……和紙は国内江手広く売り出す積り……」とあります。また、「椿紙製造商社」の創立大綱には、「……一、右製造出来立之紙売捌方之儀ハ兼而外国へ捌キ和紙ハ地方へ捌候積リ……」とあることから、彼がいう和紙とは、機械ですいた手漉き和紙風の紙を指しているのが明らかです。また、これが「和紙」という言葉の初出になります。>
このことから、このサイトでは伝統的な手法でつくられた紙を手漉き和紙、日本の手漉き紙を意識した機械抄きの紙を機械抄き和紙と表現します。
和紙には伝統的な手漉き技法(流し漉きなど)によるものと、特殊な抄紙機による機械抄きのものがあります。普段私たちが日常目にし、使用している紙(ノートや本、包装紙など)の多くが機械で抄かれた紙です。
機械抄き紙は、長網抄紙機や円網抄紙機という大型の紙抄き機械で、大量生産されています。連続的に大量生産されることにより、品質的にも安定し大量に使用、消費するのに適しています。定められた条件のもと、原料の段階から画一的に作られ、品質を一定に保った紙であると言えます。現在では、機械で抄くことができないとされていた楮(こうぞ)の繊維も機械抄きが可能となり、手漉き和紙に非常によく似た紙が作られるようになりました。これらを機械抄き和紙と呼ぶことがあります。
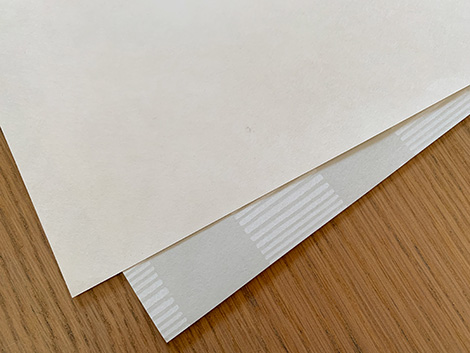
手漉き和紙は、その工程のほとんどが手作りです。和紙作りの原料は、産地やその工場によって異なり、個々の紙漉き工場で使用する分だけ処理され、パルプ化されたものを使用します。そのため、原料となる楮(こうぞ)や雁皮(がんぴ)、三椏(みつまた)の処理も人や産地によって違いが生じます。手擁き和紙は紙漉き職人が一枚一枚漉き上げます。よって人により差が生じ、それが紙の個性となって現れます。もちろん手漉き和紙の品質にばらつきがあってよいわけではなく、熟練の職人による手では同様の品質の紙を生産します。
伝統的な手漉き和紙の代表的な繊維原料は楮(こうぞ)、雁皮(がんぴ)、三椏(みつまた)です。粘剤(トロロアオイなど)を増粘剤と繊維の分散剤として用い、流し漉き法で抄紙(しょうし/意味:紙を漉くこと)したものとなります。しかしこれらの原料を使用した手漉き和紙はコスト面が割高になります。現在は、手漉き、機械抄き共に、多様な用途、生産量やコスト面からその製造方法や原料の配合などには様々なものがあります。例えば、洋紙の原料が綿ぼろから木材パルプヘ変化し、機械抄き和紙の登場、コスト面から和紙原料として木材パルプの導入などが挙げられます。これらの変化により、和紙の定義は曖昧となり、人や産地によって異なる表現や説明がなされることにも繋がっています。

印刷や筆記用の洋紙は紙面の平滑性が求められます。そのため紙としては締まったものが要求されます。一方、似た厚さの楮(こうぞ)を原料とした手漉き和紙は、あまり叩解せずに長繊維をきれいに分解させて抄紙(しょうし)することで、空気を多く含み熱伝導率が低くなり、触ると暖かく感じます。紙面は平滑ではないので、紙表面で光を拡散させて柔らかい感じを見る人に与えます。

植物の繊維には“自己接着性”があり、繊維と繊維の重なった接点は互いにくっつき合うという性質を持っています。植物繊維(セルロース)は、ブドウ糖からできており、このブドウ糖が沢山長く繋がって出来たものがセルロース分子です。これは水には溶けないが水とよくなじむ性質“親水性”があり、このセルロース分子がたくさん集まってできたものが繊維です。親水性というのは、セルロース分子のところどころに水の分子と同じ型をした部分があり、その部分と水とは良く結合するために生まれる性質です。そのため植物繊維は水となじみやすく、繊維を水に浸けると非常によく水を吸い膨張します。繊維に十分水を吸わせて、それをシート状にして乾燥させると、今まで水と結合していた繊維と繊維の接触している部分が、繊維同士の結合に変わり、ひとつひとつの結びつきは弱いが、紙全体では数えきれないほどたくさん結合するので、大きな力となり丈夫な紙ができるのです。
楮(こうぞ)繊維は針葉樹繊維に較べ長い繊維です。その細長い繊維を切断せずに水中に分散させて、簀(さく/意味:すのこ)の上に均等に漉き取る流し漉きの技術によって薄くても大変強い紙を抄紙することが出来ます。その代表例が世界中の紙製文化財の保存修復にも使われる典具帖(てんぐじょう)です。その電子顕微鏡写真をみると繊維がきれいに分散してシート状になっていることがわかります。薄く強く、保存性にも優れた紙です。
雁皮(がんぴ)や三椏(みつまた)の繊維は楮ほどではありませんが、やはり針葉樹繊維よりも長く、幅は細くなっています。雁皮はさらに多量に含まれる柔細胞が繊維間を埋めるので、良い光沢を有するなどの特徴があります。

日本には全国各地に様々な和紙の産地があり、冬場だけの紙漉き場や個人で頑張っているところ、新しい漉き場などかなりの数があります。また、残念ながら担い手がなく、生産されなくなった紙もあります。 ここでは全国手すき和紙連合会 発行『和紙の手帖』2014年7月1日発行(改訂版1刷・初版より7刷)と『和紙の手帖Ⅱ』(1996年7月20日 第1刷)に記載されている各地の紙を中心にご紹介します。